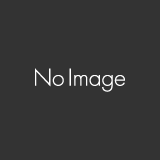大型のマンション用地を独占する(?)長谷工
- 2017.02.15
- マンション業界
このブログはマンション業界OBが業界の裏側を知り尽くした目線で、マンション購入に関する疑問や諸問題を解き明かし、後悔しないためのハウツーをご紹介・・・・原則として、毎月5と10の日に投稿しています。
新築マンションの供給戸数が大きく減っています。2016年の年間発売戸数は首都圏全体で3500戸台に留まりました。
バブル崩壊後の1992年以来24年ぶりの低水準となった模様です。
所得が伸び悩む中、人手不足に伴う建築費の上昇でマンション価格が高騰した結果、需要が冷え込み、業者が発売を絞る動きが広がったためと考えられます。前年割れは3年連続となっています。
10年前の2006年は74,463戸も新規供給がありましたが、その後は今回と同じで、価格高騰の影響から2007年:61,021戸、2008年:43,733戸と大きく減少しました。さらに、2008年秋のリーマンショックを契機に世界金融危機、世界同時不況が発生したため、2009年には、とうとう36,376戸と3年前の半分の水準へと激減してしまったのです。
2010年、2011年は4万4千戸台と回復傾向を見せました。2012年も45,602戸と同水準、そして、アベノミクスの効果もあって、2013年は久々の5万戸台(56,478戸)に増加しましたが、2014年は再び44,913戸と減少し、2015年=40,449戸、そして2016年=35,772戸と大幅に減る事態となったのです。
ここまでは、2017年1月25日の本ブログで紹介したものです。
発売減の中身は、売り出しても売れないので発売を先送りしているということでもあるのですが、建築工事は進んでいますから、いずれは販売を開始することになります。
一方、遅れている分の販売見通しが立たないうちは、新たな着工は思いとどまるはずです。何故なら在庫ばかり増やすことになるからです。 土地だけで置いておくという策を選ぶに違いありません。
としたら、この低迷状況はしばらく続くことになりそうです。
●用地がない
先述のように、発売戸数が減少した原因は価格の急騰によって需要が後退し、売れ行きが悪化したからです。価格高騰の主因は建築費の高騰でした。
しかし、もっと深く分析すると別の側面が浮かんで来ます。ここでは、簡単に二つの理由として解説することにします。
理由の第一は、用地の高騰です。適地が減って、業者間競争が激しくなり、買収価格が吊り上げられ、マンション価格高騰の一因になっているのです。
思い起こすと、良い土地が中々ないと嘆きながらも用地を確保し、マンション供給を続けて来た業者に強い順風が吹いた時期がありました。
バブル崩壊後の地価下落過程で、法人・団体は一斉に土地を放出し出したのです。
それまでは一度取得したら手放さないで抱え込むことが「含み経営」という日本企業の経営の根幹をなすものでしたが、右肩上がりの土地神話が崩壊し、並行して会計基準が国際化されたとなどによって、方針転換する企業が続出しました。
社宅、グラウンド、工場、倉庫、資材置き場、廃校や移転で空いた学校など、垂涎の土地が次々とマンション業者の手に渡りました。その結果、バブル期には殆んど途絶えていた(※)と言って過言でない新築マンションが息を吹き返したように急速に開発され、市場に送り出されたのです。
(※1991年の首都圏の新規発売戸数は2016年の戸数を下回る26,248戸だった)
2000年(95,635戸)からリーマンショック前年の2007年までの年間供給戸数は、平均80,000戸を超えることとなりました。首都圏の年間需要は50,000戸くらいと言われていましたが、バブル期の供給不足がウエイティング需要を蓄積させていたことによって爆発的な売れ行きをもたらしたのです。
ところが、その後は地価の高騰もあってマンション用地は極端に減少しました。企業のリストラ(土地の置き換え・単純放出)が一巡してしまったのです。特に大規模敷地は湾岸エリアに限られてしまったかのようです。
理由の二番目は、中小デベロッパーの減少です。つまり、作り手がいなくなったのです。2008年秋に起きた「リーマンショック」は世界金融危機と世界同時不況を招きました。
日本も例外ではなく、百年に一度の不景気が来るとの危機感が広がり、とりわけ金融機関はバブル崩壊の過程で巨額の不良債権を抱えてしまった経験から、守りの姿勢を強めました。その影響を最も強く受けたのが、負債比率の高い中小マンション業者とゼネコンでした。
マンション供給戸数で一度は大手「大京」を抜いて全国一位になったこともある穴吹工務店を筆頭に、個性派のマンション業者が株式上場企業も含めて銀行から資金を止められ、多数倒産してしまいました。
大手は大規模マンションを、中小は大手が手を出さないエリアと中規模以下のマンションをと住み分けしていた業界でしたが、その構図が崩れ、中小業者の分がごっそりと減ったのです。
(穴吹工務店は、現在、株式会社大京の傘下で再建中)
発売状況を見ていると、中小デベロッパーの中に台頭して来たと感じる企業も何社か見られますが、全体的には力不足です。かつて、首都圏だけでマンションデベロッパーは500社も存在しましたが、その大半は中小企業だったのです。倒産、清算、廃業、本業回帰(休業)の形で姿を消したというわけです。
全盛期に戻ることはないにしても、中小デベロッパーが多数再参入し、用地確保に力を注ぐことでマンション供給量を増やす先鋒になるに違いないと思うのです。
●用地難を読み取った長谷工コーポレーションの暗躍
少ない用地を先回りして買い取っている企業がああります。その名は、マンション施工日本一を謳う長谷工コーポレーションです。
これは同社の昔からのビジネスモデルなのですが、デベロッパーが買いに来る前に、めぼしい土地(主に敷地の大きな倉庫・工場跡地)を買っておき、その後にプラン付き・採算計画付きでデベロッパーに持ち込むのです。無論、建築工事の特命発注が条件です。
長谷工コーポレーションは、用地難が来ると読んだのでしょう。以前にも増して用地の先行取得に走ったようです。
その結果、大規模マンションの多くは、右を向いても左を向いても長谷工コーポレーション施工なのです。首都圏のマンション工事の20数%は長谷工コーポレーションが占めると自ら公表した同社ですが、最近は30%を超えているのではないかと見られます。
一体、マンションデベロッパーは何をしているのでしょうか? 長谷工案件は、大半が倉庫や工場跡地なのです。その種の土地が売りに出るという情報を何故キャッチできないのでしょうか、その気になれば先んじることは大手なら可能なはずです。
業界の外へ出た筆者でも3年前には、長谷工だらけになることを予測することができました。その予想を、このブログでも開陳したのですが、予想以上の実態となっています。
長谷工コーポレーションとのコラボが悪いというわけではありませんが、規格型マンションが得意技の同社とでは、個性的で魅力に溢れる商品は期待できないのです。
はっきり言えば、つまらんマンションが多いのです。これが住友ブランドなのか、野村のプラウドがこれかなどと落胆してしまうばかりです。
デベロッパー各位の自助努力に期待したい、そして安く優良なマンション開発を鶴首して待ちたい。筆者は今、そんな気分です。
・・・・今日はここまでです。ご購読ありがとうございました。ご質問・ご相談は「無料相談」のできる三井健太のマンション相談室(http://www.syuppanservice.com)までお気軽にどうぞ。
★★★三井健太の「名作間取り選」はこちら
https://mituimadori.blogspot.com
★★★「三井健太の住みたいマンション」はこちら
https://sumitaimansion.blogspot.com
完成内覧会の立会サービスを「格安」で。ただいま予約受付中!!
詳細はホームページのトップにある「メニュー」内の「内覧会立会いサービス」をクリックするとご覧になれます。こちら・・・http://www.syuppanservice.com
舞い上がってしまいそう。そんなときの「マンション評価サービス」無料
気に入った。買いたい。欲しい。そんなときこそ立ち止まって見ましょう。
第三者の客観的な視点は、きっとお役に立つに違いありません。
お申込みは上記URLから(無料の範囲は限られます:ご注意ください)
)
※※マンション購入を真剣に考えるブログでお馴染みの「のらえもん」さんが新サービスを開始しました。
豊洲・東雲・有明・晴海・勝どきの湾岸タワーマンションを中心に、グルメやイベントなどの周辺地域情報を取り上げた「湾岸総合情報ブログ」はのらえもんさんが運営しています。
そののらえもんさんが、消費者のための住宅購入応援サービス「住まいスタジアム」はじめました。これは「独立系FP+住宅アドバイザー」のサービスです。対面形式の相談です。三井健太も協力しています。詳細こちらから。